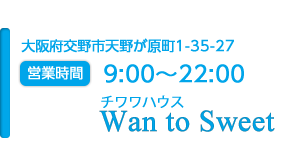チワワで気をつけたい病気new
病気に関するご質問には、基本的なことをお答えしております。何か症状が出ていて気になる、または詳しく知りたいという場合には動物病院での受診をお勧めします。
ワクチンの必要性はわかるのですが、チワワは小さい分、副反応も気になっています。
![]() 人であっても、犬であっても、ワクチンによる副反応はゼロとは言えず、心配にもなりますね。American Veterinary Medical Association(AVMA)のホームページにあるワクチン接種後の副反応に関する説明を見てみると、主に以下のような症状が見られる場合もあるとのことです。
人であっても、犬であっても、ワクチンによる副反応はゼロとは言えず、心配にもなりますね。American Veterinary Medical Association(AVMA)のホームページにあるワクチン接種後の副反応に関する説明を見てみると、主に以下のような症状が見られる場合もあるとのことです。
軽度の服反応:
・ワクチンを接種した箇所の不快感や局所的な腫れ。
・微熱。
・食欲や元気の低下。
・鼻腔内ワクチンの場合、2~5日後にくしゃみ、軽い咳、鼻水などが見られる。
深刻な状態で、すぐに動物病院へ連れて行く必要がある副反応:
・持続的な嘔吐や下痢。
・蕁麻疹。
・口吻、顔、目の周り、首などの腫れ。
・重度の咳や呼吸困難。
・虚脱状態。
(出典:AVMA / What to Expect After Your Pet’s Vaccination)
2005年のものではありますが、アメリカのパデュー大学の研究チームが約123万頭の犬に対して、ワクチン接種後3日間で発症した副反応について調査したところ、体重が軽くなるにつれて副反応のリスクが高まるということを見出したそうです。その中で、特にリスクの高い犬種は、チワワ、ダックスフンド、パグ、ボストン・テリア、ミニチュア・ピンシャーなどで、体重10kg以下の犬は体重10kg~45kgの犬と比較して、リスクはおよそ倍になるとか(*)。
かと言って、ワクチンを接種せずにいれば感染症に罹るリスクのほうが高まり、最悪の場合、命を落としてしまうこともあり得ます。ワクチンの副反応は必ず出るというわけでもありませんので、接種の前後には細心の注意をはらうしかないということでしょう。そのためには、主に以下のようなことにお気をつけいただければと思います。
・ワクチン接種前後の1~2週間は体調管理を怠らない。
・ワクチン接種前後の1~2週間はシャンプーをしない。
・お腹をこわしている、微熱があるなど、体調に不安がある時には接種しない。
・散歩や運動をした直後は避け、落ち着いた状態の時に動物病院へ。
・万が一、様子がおかしい時にはすぐに診てもらえるよう、接種は極力午前中に。
・ワクチン接種後は、30分~1時間程度、犬の様子を観察する。
・ワクチン接種後の散歩、運動はひかえる。
(*)Adverse events diagnosed within three days of vaccine administration in dogs / Moore GE et al. / J Am Vet Med Assoc. 2005 Oct 1:227(7):1102-8
チワワには関節系のトラブルもまま見られると聞きました。なるべく早く気づいてあげるために、見分けるポイントのようなものはありますか?
![]() ここでは関節だけでなく、運動器疾患としてお答えします。犬も高齢になると関節炎が出たりしますが、若くても運動器にトラブルが出ることもあります。整形外科に特化した獣医さんに教えていただいたポイントを以下に記しますので、参考にしてみてください。犬に以下のような様子が見られた時には、運動器疾患を患っている可能性があるそうです。もちろん、原因は他にある場合もありますが。
ここでは関節だけでなく、運動器疾患としてお答えします。犬も高齢になると関節炎が出たりしますが、若くても運動器にトラブルが出ることもあります。整形外科に特化した獣医さんに教えていただいたポイントを以下に記しますので、参考にしてみてください。犬に以下のような様子が見られた時には、運動器疾患を患っている可能性があるそうです。もちろん、原因は他にある場合もありますが。
✓ 階段の段差やソファの上り下りを嫌がる、上り下りの動作がゆっくりになった。
✓ 散歩に行きたがらない、遊ばなくなった、あまり走らなくなった。
✓ 立ち上がる時にもたつく、辛そうである。
✓ 元気がない、動きたがらない。
✓ しっぽを下げていることが多い。
✓ 寝ている時間が多くなった、逆に短くなった。
特に、慢性的な痛みがある場合は、痛いがために起きては寝るを繰り返すことから、寝ている時間が多くなる、またはなかなか寝られずに起きているということがあるようです。また、前肢や後肢の幅が以前より狭くなった、逆に広くなったという場合も慢性的な痛みがあるのでは?と疑えるそうです。その他、前脚を痛そうにしている場合、歩く時の頭の上下動を見ることで、どちらの足が痛いのかを推測できるとか。頭が下がっている時に地面についている脚は正常で、頭が上がっている時に地面についている脚が痛いのだそうです。ともあれ、そのような病気にはかからないのが一番。生活環境や運動、体重管理などに気配りして、予防を心がけてください。
チワワは骨が細いですし、今後のことを考え、関節系トラブル予防の意味も含めてサプリメントを使おうか考えています。
![]() 関節系トラブルと言えば、確かにチワワは膝蓋骨脱臼における好発犬種の1つとして挙げられています。関節系に効果があるとされる成分の入ったサプリメントを使ってみるのもよろしいかと思いますが、分子量の違いや、犬用としてきちんと効果が研究された製品であるかどうかということはチェックすることをお勧めします。分子量は吸収率に関係しますので、折角使用するのであるならば、より効果が期待できるよう、なるべく吸収率も高い分子量のものをお使いになるのがよろしいのではないでしょうか。なお、サプリメントを摂取していれば、それで大丈夫というわけでもありません。併せて食事や運動、生活環境、体重管理などにも考慮が必要でしょう。ちなみに、明治大学が行った日本の犬の肥満度調査(2016)では、オス犬にくらべてメス犬は1.3倍肥満度が高く、肥満ではミニチュア・ダックスフンドに次いでチワワが、また、太り過ぎの犬としてはチワワがもっとも多かったそうなので、関節に負担をかけないよう、体重管理には気をつけたいですね。
関節系トラブルと言えば、確かにチワワは膝蓋骨脱臼における好発犬種の1つとして挙げられています。関節系に効果があるとされる成分の入ったサプリメントを使ってみるのもよろしいかと思いますが、分子量の違いや、犬用としてきちんと効果が研究された製品であるかどうかということはチェックすることをお勧めします。分子量は吸収率に関係しますので、折角使用するのであるならば、より効果が期待できるよう、なるべく吸収率も高い分子量のものをお使いになるのがよろしいのではないでしょうか。なお、サプリメントを摂取していれば、それで大丈夫というわけでもありません。併せて食事や運動、生活環境、体重管理などにも考慮が必要でしょう。ちなみに、明治大学が行った日本の犬の肥満度調査(2016)では、オス犬にくらべてメス犬は1.3倍肥満度が高く、肥満ではミニチュア・ダックスフンドに次いでチワワが、また、太り過ぎの犬としてはチワワがもっとも多かったそうなので、関節に負担をかけないよう、体重管理には気をつけたいですね。
先日、チワワには逆くしゃみと呼ばれるものが見られることがあると聞いたのですが、何のことでしょうか?
![]() 人間で言うくしゃみとは違って、突然、鼻をズーズー、ブーブーと慣らして息を吸い込むような仕草が見られることがあり、この症状のことを一般的に逆くしゃみ(逆くしゃみ症候群/revers sneeze syndrome/revers sneezing)と言っています。チワワに限らず、特に鼻の短い短吻種や小型犬に多いとされていますが、獣医師に聞いたところによると、病気というわけではなく、例えて言うなら人間のひゃっくりのようなものということです。原因は喉に近い鼻の奥周辺の痙攣やアレルギーなどが考えられているものの、はっきりとはわかっていないとのこと。症状は数十秒~数分程度で治まることが多く、元に戻れば犬もけろっとしています。ただ、似たように思えるものでも、ケッケッと何かを吐き出すようにする症状(犬では咳と言われます)や、アヒルの鳴き声のようなガーガーという音が続く場合は心臓や気管などに病気がある可能性も考えられるので、その場合には治療が必要になるでしょう。いずれにしても、気になるようでしたら動物病院で診てもらうことをお勧めします。
人間で言うくしゃみとは違って、突然、鼻をズーズー、ブーブーと慣らして息を吸い込むような仕草が見られることがあり、この症状のことを一般的に逆くしゃみ(逆くしゃみ症候群/revers sneeze syndrome/revers sneezing)と言っています。チワワに限らず、特に鼻の短い短吻種や小型犬に多いとされていますが、獣医師に聞いたところによると、病気というわけではなく、例えて言うなら人間のひゃっくりのようなものということです。原因は喉に近い鼻の奥周辺の痙攣やアレルギーなどが考えられているものの、はっきりとはわかっていないとのこと。症状は数十秒~数分程度で治まることが多く、元に戻れば犬もけろっとしています。ただ、似たように思えるものでも、ケッケッと何かを吐き出すようにする症状(犬では咳と言われます)や、アヒルの鳴き声のようなガーガーという音が続く場合は心臓や気管などに病気がある可能性も考えられるので、その場合には治療が必要になるでしょう。いずれにしても、気になるようでしたら動物病院で診てもらうことをお勧めします。
チワワは体が小さいので気になるのですが、狂犬病予防注射は必ず接種しないといけないのでしょうか?
new
![]() 『狂犬病予防法』という法律では、居住する市区町村に犬の登録をすることと、年に1回狂犬病予防注射をすること、その際に発行される鑑札や注射済票を犬に装着することが義務づけられています。ということは、体の小さいチワワであってもそれが適用されるということになります。しかし、1957年を最後に日本では狂犬病が発生していないということもあって、近年では接種率が下がり、実質的には50%以下(登録している犬で計算すると約70%)になっていると言われます。一方で、日本が狂犬病の発生していない国および地域として指定しているのは、日本を除き、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、グァム、ハワイ、アイスランドの6地域のみで、以前はそれに含まれていたノルウェー、アイルランド、スウェーデン、イギリスは2012年に、台湾は2013年に削除されています(農林水産省より)。少なくとも、他の多くの国々では未だに存在する怖い感染症なのだということは心に留めておく必要はあるでしょう。ちなみに、WHOでは2030年までに狂犬病による死亡者ゼロを目指した国際的な取り組みが2015年より始まっているそうです。
『狂犬病予防法』という法律では、居住する市区町村に犬の登録をすることと、年に1回狂犬病予防注射をすること、その際に発行される鑑札や注射済票を犬に装着することが義務づけられています。ということは、体の小さいチワワであってもそれが適用されるということになります。しかし、1957年を最後に日本では狂犬病が発生していないということもあって、近年では接種率が下がり、実質的には50%以下(登録している犬で計算すると約70%)になっていると言われます。一方で、日本が狂犬病の発生していない国および地域として指定しているのは、日本を除き、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、グァム、ハワイ、アイスランドの6地域のみで、以前はそれに含まれていたノルウェー、アイルランド、スウェーデン、イギリスは2012年に、台湾は2013年に削除されています(農林水産省より)。少なくとも、他の多くの国々では未だに存在する怖い感染症なのだということは心に留めておく必要はあるでしょう。ちなみに、WHOでは2030年までに狂犬病による死亡者ゼロを目指した国際的な取り組みが2015年より始まっているそうです。
そうした中で、予防注射で犬にショック反応が出る、高齢や病気などがあって打てないというケースもあります。狂犬病予防注射猶予証明書(獣医師の診断が必要)というものを提出することで、一定期間、注射を免除してもらうことも可能となっている自治体も結構ありますので、接種をためらう場合、詳しくは動物病院で相談なさってみてください。
うちのチワワは歯が重なって生えています。
![]() 子犬の歯は生後21日頃から生えはじめ、生後2ヶ月ほどで乳歯が生えそろいます。永久歯が生えはじめるのは生後4~5ヶ月からで、生後7~8ヶ月頃には乳歯と永久歯が生え代わります。通常であれば抜け落ちてしまうはずの乳歯が残ってしまい、永久歯と並んで生えている状態を乳歯遺残と言います。小動物の歯に詳しい獣医さんによると、人間では乳歯が抜けた後に永久歯が生えてくるのに対して、犬の場合は乳歯と永久歯が併存して生えている期間があるそうです(犬歯=1~2週間/切歯・臼歯=0~2日程度)。永久歯が生えてきた後、この期間を過ぎても乳歯が残っているということであれば、乳歯遺残になるでしょう。これは特にチワワのような小型犬に多く、また、歯並びが正常ではない(歯の向きが違ったり、がちゃがちゃに生えていたりなど)不正咬合も同様に多いと言われます。元々小型犬は歯と歯の間の隙間が狭く、さらに乳歯遺残や不正咬合があると歯垢がたまりやすい上、歯周病のリスクが高まりますので、歯磨きは定期的にしてあげたいものです(犬の場合、歯垢が歯石へと変わるのは3~5日。少なくとも1日おきに歯磨きをするのが望ましいそうです)。動物病院では早めに乳歯を抜くことを勧めると思いますが、なるべく犬の歯に理解が深い動物病院でご相談なさることをお勧めします。
子犬の歯は生後21日頃から生えはじめ、生後2ヶ月ほどで乳歯が生えそろいます。永久歯が生えはじめるのは生後4~5ヶ月からで、生後7~8ヶ月頃には乳歯と永久歯が生え代わります。通常であれば抜け落ちてしまうはずの乳歯が残ってしまい、永久歯と並んで生えている状態を乳歯遺残と言います。小動物の歯に詳しい獣医さんによると、人間では乳歯が抜けた後に永久歯が生えてくるのに対して、犬の場合は乳歯と永久歯が併存して生えている期間があるそうです(犬歯=1~2週間/切歯・臼歯=0~2日程度)。永久歯が生えてきた後、この期間を過ぎても乳歯が残っているということであれば、乳歯遺残になるでしょう。これは特にチワワのような小型犬に多く、また、歯並びが正常ではない(歯の向きが違ったり、がちゃがちゃに生えていたりなど)不正咬合も同様に多いと言われます。元々小型犬は歯と歯の間の隙間が狭く、さらに乳歯遺残や不正咬合があると歯垢がたまりやすい上、歯周病のリスクが高まりますので、歯磨きは定期的にしてあげたいものです(犬の場合、歯垢が歯石へと変わるのは3~5日。少なくとも1日おきに歯磨きをするのが望ましいそうです)。動物病院では早めに乳歯を抜くことを勧めると思いますが、なるべく犬の歯に理解が深い動物病院でご相談なさることをお勧めします。
子犬の時に混合ワクチンを複数回接種するのはなぜですか?
![]() 子犬は母犬の初乳を飲むことによって(一部には胎盤を通じて)、移行抗体を譲り受け、当面の間は感染症に対抗できるだけの体になっていますが、この抗体は生後2~4ヶ月齢くらいまでの間に徐々に消えていってしまうのです。
子犬は母犬の初乳を飲むことによって(一部には胎盤を通じて)、移行抗体を譲り受け、当面の間は感染症に対抗できるだけの体になっていますが、この抗体は生後2~4ヶ月齢くらいまでの間に徐々に消えていってしまうのです。
抗体がなくなると、当然感染症の危険にさらされることになりますから、その前にワクチンを接種してあげる必要があります。
ただし、難しいのが、抗体が少なくなる時期というのは子犬によってタイミングが違うということ。なぜそのタイミングが重要になるのか?というと、まだ抗体が十分残っているうちにワクチンを接種しても高い効果は得られないからです。
よって、抗体価が落ちてきそうな頃を見計らって接種する必要があり(ブースター効果)、複数回接種することで確実性を高めるというわけです。動物病院によって接種時期や接種間隔、回数には若干違いがありますが、概ね、生後6~9週齢くらいで1回目を接種し、その後は3~4週間隔で1~2回接種するのが一般的なようです。
ちなみに、世界小動物獣医師会(WSAVA)のワクチネーションガイドラインでは、すべての犬に接種するべきとする重要度の高いコアワクチン(犬ジステンパー、犬パルボウィルス、犬アデノウィルス、日本では法律で義務化されていることから狂犬病も)と、地域性やライフスタイルによって接種を選択するノンコアワクチンとに分けています。
チワワでも歯磨きが必要ですか? 口が小さ過ぎて思うように磨けません。
![]() 3歳以上の成犬の80%は歯周病になっているか、それが心配される状況であると言われています。小型犬は歯と歯の間の隙間も狭くなっているため汚れもたまりやすく、その分、歯周病にもなりやすいそうです。犬も年をとったら歯も傷んでだんだんと抜けていくものだと思ったら大間違い。歯周病を放置してしまうと、毒素が血流に乗って全身へと回り、心臓病や肝臓病など様々なものに悪影響を及ぼしてしまいますので、歯を健康に保つということは全身の健康にもつながります。最初は口の周りや口の中を触っても大丈夫なように慣らしてから、徐々にガーゼや歯ブラシで磨くようにするのがいいと思います。チワワは口が小さいですから、人間の子供(赤ちゃん)用のものか、歯間ブラシで代用できます。口をなかなか開けない場合でも、唇の端からスッと歯ブラシを入れると結構入ります。とりあえず磨けるところだけでも磨いておくのがいいのではないでしょうか。
3歳以上の成犬の80%は歯周病になっているか、それが心配される状況であると言われています。小型犬は歯と歯の間の隙間も狭くなっているため汚れもたまりやすく、その分、歯周病にもなりやすいそうです。犬も年をとったら歯も傷んでだんだんと抜けていくものだと思ったら大間違い。歯周病を放置してしまうと、毒素が血流に乗って全身へと回り、心臓病や肝臓病など様々なものに悪影響を及ぼしてしまいますので、歯を健康に保つということは全身の健康にもつながります。最初は口の周りや口の中を触っても大丈夫なように慣らしてから、徐々にガーゼや歯ブラシで磨くようにするのがいいと思います。チワワは口が小さいですから、人間の子供(赤ちゃん)用のものか、歯間ブラシで代用できます。口をなかなか開けない場合でも、唇の端からスッと歯ブラシを入れると結構入ります。とりあえず磨けるところだけでも磨いておくのがいいのではないでしょうか。
元気がよ過ぎて高い所も平気でジャンプします。関節や骨が心配になるのですが。
![]() 小型犬に多いとされる膝蓋骨脱臼はチワワでも発症することがあります。先天性と後天性のものがあるのですが、重度になると手術が必要になる場合もあります。関節にとってよくないとされるのは滑りやすい床や太り過ぎです。すでに症状が出ている場合には、ジャンプも極力やめさせたほうがいいでしょう。滑りやすい床で生活している犬とそうでない犬、また肥満の犬とそうでない犬とでは、関節系のトラブルの発症率が違うと言いますから、滑りにくい床にするなど生活環境を整えるとともに、肥満にさせないように注意することが大切です。人間から見るとチワワはかなり小食ですので、ついもう一口与えたくなりますが、与え過ぎにはお気をつけください。なお、バランスがとれているフードであれば、敢えてカルシウム剤を足さなくても大丈夫です。
小型犬に多いとされる膝蓋骨脱臼はチワワでも発症することがあります。先天性と後天性のものがあるのですが、重度になると手術が必要になる場合もあります。関節にとってよくないとされるのは滑りやすい床や太り過ぎです。すでに症状が出ている場合には、ジャンプも極力やめさせたほうがいいでしょう。滑りやすい床で生活している犬とそうでない犬、また肥満の犬とそうでない犬とでは、関節系のトラブルの発症率が違うと言いますから、滑りにくい床にするなど生活環境を整えるとともに、肥満にさせないように注意することが大切です。人間から見るとチワワはかなり小食ですので、ついもう一口与えたくなりますが、与え過ぎにはお気をつけください。なお、バランスがとれているフードであれば、敢えてカルシウム剤を足さなくても大丈夫です。
チワワに興味があるのですが、水頭症が気になります。
![]() 水頭症はチワワに限らず、ポメラニアンやヨークシャー・テリア、マルチーズ、パグ、ミニチュア・ダックスフンド、トイ・プードルなど小型犬に発症が見られる他、大型犬でも発症することがあるそうです。先天性と後天性のものがあり、脳室内に脳脊髄液が溜まってしまうことから脳室が広がり、脳の組織を圧迫してしまいます。その結果、元気がない、ふらつくなどの症状が見られ、重症になると歩行障害や痙攣発作、失明などの他、昏睡状態に陥ることもあります。意識レベルの低下により、しつけをしてもなかなか覚えないということがありますので、どうしてもしつけがうまくいかない、かつ活力もないという場合には、一度動物病院で診てもらったほうがいいでしょう。水頭症をもった犬では頭頂部の骨がくっついておらず、穴が開いている(泉門の開存/モレラ)ことが多いということですが、人間と同じように犬も生まれたての頃は泉門が開いており、多くが成長とともに閉じていきます。閉じきらずに泉門が開いたままであっても、それがイコール水頭症になるというわけではありません。何の問題もなく元気に暮らしているチワワはたくさんいます。ただ、泉門が開いたままになっている犬では、頭部に強い刺激を与えるようなことは避けたほうがいいでしょう。
水頭症はチワワに限らず、ポメラニアンやヨークシャー・テリア、マルチーズ、パグ、ミニチュア・ダックスフンド、トイ・プードルなど小型犬に発症が見られる他、大型犬でも発症することがあるそうです。先天性と後天性のものがあり、脳室内に脳脊髄液が溜まってしまうことから脳室が広がり、脳の組織を圧迫してしまいます。その結果、元気がない、ふらつくなどの症状が見られ、重症になると歩行障害や痙攣発作、失明などの他、昏睡状態に陥ることもあります。意識レベルの低下により、しつけをしてもなかなか覚えないということがありますので、どうしてもしつけがうまくいかない、かつ活力もないという場合には、一度動物病院で診てもらったほうがいいでしょう。水頭症をもった犬では頭頂部の骨がくっついておらず、穴が開いている(泉門の開存/モレラ)ことが多いということですが、人間と同じように犬も生まれたての頃は泉門が開いており、多くが成長とともに閉じていきます。閉じきらずに泉門が開いたままであっても、それがイコール水頭症になるというわけではありません。何の問題もなく元気に暮らしているチワワはたくさんいます。ただ、泉門が開いたままになっている犬では、頭部に強い刺激を与えるようなことは避けたほうがいいでしょう。
チワワは低血糖症になりやすいと聞いたのですが。
![]() 低血糖症は成犬でも起こることがありますが、特に生後3ヶ月齢くらいまでの子犬に起こりやすく、中でもチワワでは発症率が高い傾向にあります。下痢や嘔吐、食事量や回数および内容の不足、気温の低下、遊び過ぎ、ストレスなどが原因となって、血中の糖分濃度が低下することから、ぐったりして元気がなくなる、痙攣や麻痺といった症状が見られるようになります(糖質は脳や筋肉にとって重要なエネルギー源)。手当てが遅れると死に至ることがあるため注意を要します。もし低血糖症らしき様子が見られた時には、応急処置として砂糖水や蜂蜜を口にふくませ、保温と安静を心がけるという方法もありますが、なるべく早めに動物病院で診てもらってください。特に子犬を迎えた直後はついかまいたくなるものです。子犬はまだ疲れの加減がわからずに遊び続けますから、かまい過ぎないように、そしてしっかり休息できる場所や時間を確保できるように配慮してあげてください。
低血糖症は成犬でも起こることがありますが、特に生後3ヶ月齢くらいまでの子犬に起こりやすく、中でもチワワでは発症率が高い傾向にあります。下痢や嘔吐、食事量や回数および内容の不足、気温の低下、遊び過ぎ、ストレスなどが原因となって、血中の糖分濃度が低下することから、ぐったりして元気がなくなる、痙攣や麻痺といった症状が見られるようになります(糖質は脳や筋肉にとって重要なエネルギー源)。手当てが遅れると死に至ることがあるため注意を要します。もし低血糖症らしき様子が見られた時には、応急処置として砂糖水や蜂蜜を口にふくませ、保温と安静を心がけるという方法もありますが、なるべく早めに動物病院で診てもらってください。特に子犬を迎えた直後はついかまいたくなるものです。子犬はまだ疲れの加減がわからずに遊び続けますから、かまい過ぎないように、そしてしっかり休息できる場所や時間を確保できるように配慮してあげてください。